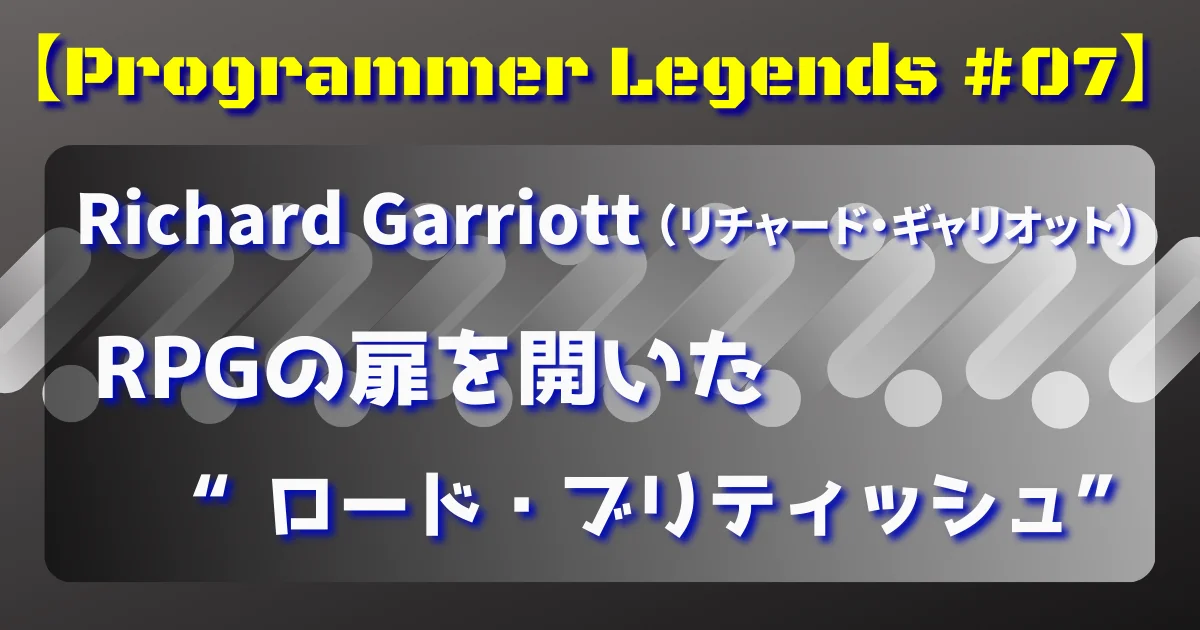
コードで世界を形にした“最初の数年”
リチャード・ギャリオット(ロード・ブリティッシュ)が「プログラマーレジェンド」と呼ばれるのは、趣味から始めた Akalabeth を経て、その後の Ultima I へと繋ぐ初期の数年である。ここでは、彼が一人でどのような思考と行動で RPG の骨格をプログラムに落とし込んだか、その実際を掘る。

リチャード・ギャリオット - Wikipedia
(Richard Garriott de Cayeux、1961年7月4日 - )は、イギリス生まれのアメリカ合衆国のゲームクリエイター。とりわけコンピュータ用ロールプレイングゲーム(RPG)に発する「ウルティマ」シリーズの作者として知られている。
https://w.wiki/FQqD高校卒業直後(1979年夏)、ガリオットは Apple II を手に入れ、Applesoft BASIC で最初の RPG、『Akalabeth: World of Doom』を趣味として書き始めた。 彼は高校時代、小さな「D&D系ゲーム」を多数制作しており、その中のひとつが Akalabeth へと発展していく。
Akalabeth: World of Doom - Wikipedia
Akalabeth: World of Doom (/əˈkæləbɛθ/) is a role-playing video game created in 1979 for the Apple II by Richard Garriott, and published by California Pacific Computer Company in 1980.[1] Garriott designed the game as a hobbyist project, which is now recognized as one of the earliest known examples of a role-playing video game[2] and as a predecessor of the Ultima series of games that started Garriott's career.[3][4] Garriott is the sole author of the game, with the exception of title artwork by Keith Zabalaoui.[5]
https://en.wikipedia.org/wiki/Akalabeth:_World_of_Doom
Apple II - Wikipedia
Apple II(アップル・ツー)は、Appleが1977年に発表したパーソナルコンピューター(ないしホームコンピューター)。当時の分類としてはマイクロコンピューターである。「Apple ][」と表記されることもあるが、これは実機の筐体蓋の金属プレートのロゴの形状を模したもの。また、起動時にもディスプレイ上にこのように表示されていた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Apple_IIAkalabeth の地下迷宮部分では、ワイヤーフレームの擬似3D表示を導入。 上空のマップや街の探索、装備品購入、魔法アイテム、食料管理など、後の Ultima シリーズで定番となる要素がここに生えていた。

また、マニュアルやカバーアートを手作りし、Ziploc の袋入りで販売するなど、自作・自販形式でリリースした。彼自身が印刷所で印刷し、母親と手作業で組み立てたという逸話も残っている。

The History of Ultima Part 1: Humble Beginnings and Zip-Top Bags - Old School Gamer Magazine
Spread the loveThe humble plastic zip-top bag is great for storing a sandwich, but what does it have to do with old school gaming? Quite a bit, in fact! Back in 1979, a young man programmed a video game that was distributed in a zip-top bag, which would come to spawn a trilogy of trilogies, […]
https://www.oldschoolgamermagazine.com/the-history-of-ultima-part-1-humble-beginnings-and-zip-top-bags/?utm_source=chatgpt.comAkalabeth の成功(約 30,000 本の売上)を受けて、大学進学後すぐに Ultima I の制作に取りかかることになる。
大学1年生の時期、Ken W. Arnold の協力を得て、Akalabeth のコードや概念を下敷きにしながら、ゲームの外見・クエスト・ユーザーインターフェイスなど冒険の“体験”を拡張した作品が Ultima I である。
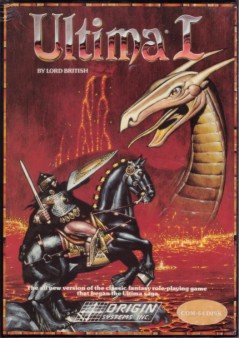
Ultima I: The First Age of Darkness - Wikipedia
Ultima, later known as Ultima I: The First Age of Darkness or simply Ultima I, is the first game in the Ultima series of role-playing video games created by Richard Garriott, originally released for the Apple II. It was first published in the United States by California Pacific Computer Company, which registered a copyright for the game on September 2, 1980[1] and officially released it in June 1981.[2] Since its release, the game has been completely re-coded and ported to many different platforms. The 1986 re-code of Ultima is the most commonly known and available version of the game.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultima_I:_The_First_Age_of_Darknessこの期間こそ、ガリオットが「好きだった D&D を自分のゲームとして実装し、商用にも耐える形へ作り上げた」瞬間の連続だった。
技術的制約(BASIC の速度、グラフィックの制御、記憶装置の容量など)を抱えながらも、彼は「遊びとしてではなく世界として機能する RPG」をプログラミングしたのである。

BASIC - Wikipedia
BASIC(ベーシック)は、手続き型プログラミング言語のひとつ。名前は「beginners' all-purpose symbolic instruction code」のバクロニムである。日本語では「初心者向け汎用記号命令コード」を意味する。
https://ja.wikipedia.org/wiki/BASICAkalabeth(1979–80):高校生が作ったRPGの原点
出自
ギャリオットは高校時代に28本以上のD&D風ゲームをBASICで作っており、その延長として『Akalabeth』を生んだ。Apple II と Applesoft BASIC を駆使し、地上はトップダウンのマップ、地下はワイヤーフレームの疑似3Dダンジョンを描画するという革新的な構造を実装した。

Revisiting: Akalabeth: World of Doom (1980)
A blog in which a dedicated addict plays through all PC computer role-playing games (CRPGs), in chronological order.
https://crpgaddict.blogspot.com/2013/03/revisiting-akalabeth-world-of-doom-1980.html?utm_source=chatgpt.com技術的挑戦
Apple II の制約下で擬似3Dを動かすため、線分描画を駆使し「動く迷宮」を見せた。当時のRPGは文字ベースが主流だったため、これは視覚表現の飛躍だった。さらに食料や装備の管理など、“生き延びる仕組み”を数値で制御した点も先駆的だった。
頒布から商業へ
最初は母親のタイプライターで説明書を打ち、ビニール袋(Ziploc)に入れて手売りした。地元の ComputerLand 店で売られ、来店していた California Pacific Computer Co. の担当者に拾われて商業化される。
1980年に正式リリースされ、約3万本が売れたとされる。
ここで重要なのは、「RPGの主要要素(探索/成長/地上と地下の二重構造)」を、個人がBASICコードだけで初めて“遊べる形”に落とし込んだことだ。
これにより、“趣味のコード”が“商用RPGの設計図”へと変貌した。
Ultima I(1981):趣味から商用への拡張

Ultima I - wiki
Ultima I: The First Age of Darkness is the first official game in the series (Akalabeth being the unofficial start). It was registered for a copyright on September 2, 1980[1] and officially released it in June 1981[2] by California Pacific Computer Co. for the Apple II. Without the subsequent installments that would establish it as the first in a series, the game was originally published simply as Ultima.
https://wiki.ultimacodex.com/wiki/Ultima_I制作の背景
『Akalabeth』の成功で商業化の手応えを得たギャリオットは、大学入学直後に「本格的に売れるRPG」を意識して開発に着手。
Apple II をターゲットに、よりリッチな体験を目指した。
技術面の進化
・ ダンジョンは Akalabeth のワイヤーフレーム 3D 表示を流用・改良。
・ 地上マップは16×16のタイル制ワールドマップへ進化し、プレイヤーは城・町・洞窟・塔を探索できるようになった。
・ BASIC のみならず、処理の重い部分はアセンブリ言語で書き直し、速度を確保した。
ゲームデザインの拡張
・ 経験値によるレベルアップシステム。
・ 装備品・魔法・乗り物(馬、飛行機、宇宙船まで!)。
・ 王からのクエストを受けて魔王モンデインを倒すという明確な物語構造。
・ 宇宙に飛び立ちシューティングを行うというジャンル越境的要素もあった。
販売と影響
California Pacific から発売されヒット。
『Ultima I』はのちに「コンピュータRPGの礎」と評価され、ドラゴンクエストやファイナルファンタジーに直結する設計思想を確立した。
Akalabeth が「趣味の延長」であったのに対し、Ultima I は**「自分の好きな世界を万人に遊ばせる」**という野心を帯びていた。
BASIC+アセンブリで組まれたそのコードは、単なるプログラムではなく「RPGの型」を生んだ設計書だった。
技術的制約と工夫:Apple IIと初期Ultimaの挑戦
■ メモリの限界
Apple II の標準メモリは 4KB〜48KB。ギャリオットが最初に『Akalabeth』を組んだときは 16KB程度のRAM しかなかった。 → 膨大なデータを保持できないため、「地形やダンジョンをランダム生成するアルゴリズム」 を実装。固定データを保存する代わりに、規則性ある疑似乱数で地形を生成することで容量を節約。
■ グラフィック描画速度
当時の Apple II のグラフィックは 280×192ドット・6色。高解像度モードは処理が非常に遅く、1ドットずつ塗ると描画に時間がかかった。 → 『Akalabeth』での ワイヤーフレーム3Dダンジョンは、線分(Line)を描く最小限の演算で「3D風」に見せる工夫。ポリゴン塗りつぶしを避け、速度と表現を両立させた。
■ BASICの限界とアセンブラの導入
Applesoft BASIC は遅く、複雑な処理はすぐに限界に達した。 → 彼は ボトルネック処理だけアセンブラ(6502機械語)で書き直す 技法を使い始め、ゲームループの一部を高速化。これが後の Ultima シリーズで複雑な戦闘・移動画面を実現する基盤になった。
■ 保存メディアの制約
初期は カセットテープ保存が基本で、ロードも遅く不安定。 → 後期には フロッピーディスク対応を取り入れ、大規模なマップやセーブデータの扱いが可能に。Ultima I では「世界をまたいで冒険できる」仕組みをディスクI/Oで支えた。
Ultima II(1982):出版の混乱と“箱の作法”

Ultima II: The Revenge of the Enchantress - Wikipedia
Ultima II: The Revenge of the Enchantress, released on August 24, 1982, for the Apple II (USCO# PA-317-502), is the second role-playing video game in the Ultima series, and the second installment in Ultima's Age of Darkness trilogy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultima_II:_The_Revenge_of_the_Enchantressパブリッシャー移行
『Ultima II』は当初も California Pacific から出す予定だったが、布マップや説明書など同梱物を充実させたいギャリオットの要望と、出版側のコスト感覚が折り合わずに対立。最終的に Sierra On-Line がリリースを引き受けることになった。
California Pacific は直後に倒産し、ギャリオットはのちに権利を買い戻していく。これがのちの Origin Systems 設立(1983) へと繋がる布石になる。

Origin Systems - Wikipedia
Origin Systems, Inc. was an American video game developer based in Austin, Texas. It was founded on March 3, 1983, by Richard Garriott and his brother Robert. Origin is best known for their groundbreaking work in multiple genres of video games, such as the Ultima and Wing Commander series. The company was purchased by Electronic Arts in 1992.
https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_Systems“箱の作法”の始まり
ギャリオットは単にゲームを売るのではなく、プレイヤーが箱を開けた瞬間から「異世界に入る」体験を設計した。布マップ、厚手のマニュアル、同梱の資料。これらは「パッケージRPG文化」の出発点となり、後のウルティマや Wizardry、そして日本のドラクエやFFの特典文化にも影響を与えた。

ウィザードリィ - Wikipedia
『ウィザードリィ』(Wizardry)は、1981年に米国のサーテック社からApple II用ソフトウェアとして発売された3DダンジョンRPGのシリーズである。ロールプレイングゲーム(RPG)の発展に大きく影響したシリーズであり、日本では初期作品がドラゴンクエストシリーズ[1]やファイナルファンタジーシリーズ[2]などに影響を与えた。サーテック社より発売
https://w.wiki/FQqW技術的な位置づけ
コード面ではまだ本人の比重が大きく、Apple II を中心に BASIC+アセンブリで開発。Ultima I の延長線上にあり、革新というより「世界の広がり」と「出版物としての体裁」に重きが置かれていた。
この時期の重要性は、「プログラム=ゲーム体験」から「パッケージ全体=ゲーム体験」へと視野を広げた点にある。
まだチーム体制は整っておらず、コードの大半はギャリオット本人が書いていたが、すでに “商品としての世界観”を作る意識 が芽生えていた。
Ultima III(1983):Origin Systems創業、個人開発からチームへ
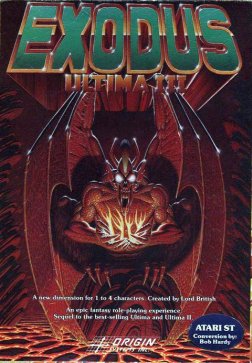
Ultima III: Exodus - Wikipedia
Ultima III: Exodus (originally released as Exodus: Ultima III) is the third game in the series of Ultima role-playing video games. Exodus is also the name of the game's principal antagonist. It is the final installment in the Age of Darkness trilogy. Released in 1983,[1] it was the first Ultima game published by Origin Systems. Originally developed for the Apple II, Exodus was eventually ported to 13 other platforms, including a NES/Famicom remake.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ultima_III:_ExodusOrigin Systems創業
『Ultima II』の出版トラブル(Sierraとの確執)を経て、ギャリオットは家族と共に Origin Systems を創業。『Ultima III: Exodus』がその最初のタイトルとなった。
以後、シリーズは自社パブリッシュに切り替わり、開発・販売の両輪を自らコントロールするようになる。

Origin Systems - Wikipedia
Origin Systems, Inc. was an American video game developer based in Austin, Texas. It was founded on March 3, 1983, by Richard Garriott and his brother Robert. Origin is best known for their groundbreaking work in multiple genres of video games, such as the Ultima and Wing Commander series. The company was purchased by Electronic Arts in 1992.
https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_Systemsチーム開発への転換
ここからはギャリオット単独のコードではなく、兄の Robert や Chuck Bueche ら仲間たちとの共同作業が進む。音楽やグラフィックも分業化され、**「一人の学生プログラマー」から「チームのディレクター」**へと役割が変化した。
技術的進化
・ プレイヤーは最大4人パーティ制で冒険(前作までは単独)。
・ 戦闘はタクティカルなターン制マップバトルに進化。
・ アセンブリを多用し、処理速度や表現力をさらに強化。
・ Apple II から他機種(Atari, Commodore 64, IBM PC)へとマルチプラットフォーム展開。

アタリ (企業) - Wikipedia
1972年にアメリカで創業されたアタリ(英語版)は、ビデオゲームを作ることを主眼に創立された会社としては世界初の企業である。同社はアーケードゲームと家庭用ゲームの開発を主軸としている一方、パソコン・ピンボール・電子ゲームも製造した。
https://w.wiki/FQtz
コモドール64 - Wikipedia
コモドール64(Commodore 64)は、コモドール社が1982年1月に発表した8ビットホームコンピューターである。C64、C=64、C-64などと略記される。CBM 64(Commodore Business Machines)あるいは VIC-64 とも称される
https://w.wiki/7bXD
IBM PC - Wikipedia
IBM PC(IBMピーシー、英: IBM Personal Computer)は、IBMが1981年に発表したパーソナルコンピュータ (PC)。IBMが最初に発売したPCであり、PCのデファクト・スタンダードとなったIBM PC互換機の先祖でもある。略称は単にPC(英: the PC)等。
https://ja.wikipedia.org/wiki/IBM_PC影響と評価
『Ultima III』は北米だけでなく日本でも注目され、後の 『ドラゴンクエスト』に強い影響を与えたと堀井雄二も語っている。特に「パーティ制」「シナリオの骨格」「フィールドとダンジョンの両立」は、JRPGの基本設計へと直結した。

ドラゴンクエスト - Wikipedia
本作は疑似マルチウィンドウ型のメニュー、パソコン用RPG『ウルティマ』に代表される二次元マップのカーソル移動を基盤としたキャラクターの移動、同じくパソコン用RPG『ウィザードリィ』に代表される対話式の戦闘モードなどといったスタイルを、当時の技術レベルでの512kbit(64KB)という、2000年代ごろにおけるフィーチャーフォンの待受画像1枚分相当のROM容量の中で実現させた作品である
https://w.wiki/FQty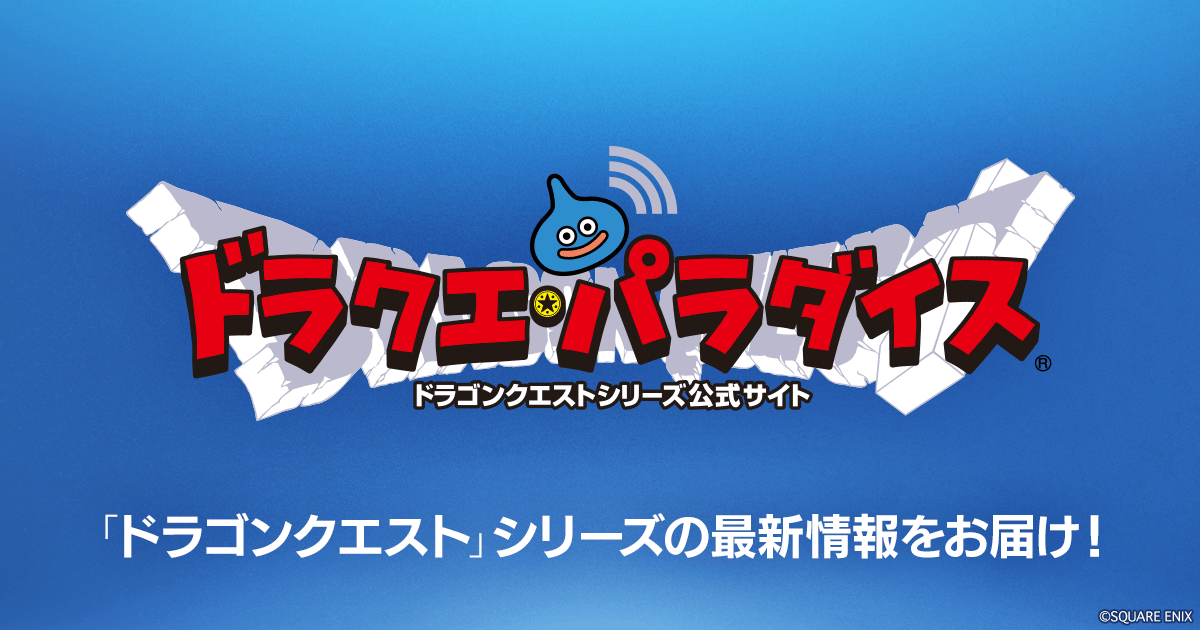
ドラクエ・パラダイス(ドラパラ)ドラゴンクエスト公式サイト | SQUARE ENIX
ドラゴンクエストの最新情報をドラパラで配信中!ドラゴンクエストシリーズの公式サイト
https://www.dragonquest.jp/ここを境に、ギャリオットは徐々に ディレクター/ワールドビルダーとしての色を強めていく。
技術的・思想的ブレイクスルー
BASICからアセンブリへ
高校生のギャリオットは Applesoft BASIC だけで Akalabeth を作った。しかし Ultima I では、計算量の多い描画処理やゲームループをアセンブリに置き換え、処理速度を大幅に向上させた。これは「遊べる速度」を確保するための必然の選択であり、同時代の学生開発者に比べて突出していた【web†source】。
「世界を持ったゲーム」への転換
それまでのコンピュータゲームは、スコアを競うアーケード型か、迷路・戦闘の単発的シミュレーションが主流だった。ギャリオットはそこに「城と町、NPC、買い物、食料、時間の経過」を導入し、持続する世界を提示した。これは後の RPG が前提とする枠組みをほぼ一人で形にしたことを意味する。
“遊び”から“物語”へ
Akalabeth の頃は「ダンジョンで生き延びる」だけだったが、Ultima I では「王からの依頼」「ラスボス・モンデインの存在」という目的と物語の骨格を持たせた。以後の RPG に必須となる「プレイヤーのロール(役割)」がここで確立した。
個人コードがジャンルを生んだ事実
当時のギャリオットはまだ大学生。趣味の延長で書いたコードが、後のドラクエやFFに直接的な設計影響を与え、「コンピュータRPG」という新しいジャンルのひな型になった。
つまり彼の功績は、奇抜なアイデア以上に、「個人のBASIC/アセンブリコードが、世界的ゲームジャンルの共通基盤になった」ことにある。
まとめ
リチャード・ギャリオットはしばしば「奇人・冒険者」として語られる。
自宅にダンジョンを作った話、宇宙旅行へ行った話…。
だが、プログラマーレジェンドとしての真価は高校〜大学初期の数年に凝縮されている。
- BASIC とアセンブリだけで「世界を持ったRPG」を一人で作った。
- Akalabeth と Ultima I の設計感覚が、ドラクエやFFの基盤を形作った。
- 趣味のコードがジャンルを生み、商業化された最初の瞬間を担った。
以降の彼はチームを率い、世界観や社会的テーマを盛り込んで Ultima シリーズを拡張していく。
しかし「個人プログラマ」としての輝きは、この最初の挑戦にこそある。
だからこそ、ギャリオットを「プログラマーレジェンド」と呼ぶなら、冒険者の人生ではなく、“コードで世界を作った若き数年間” を押さえておく必要があるのだ。
以降の話は“別シリーズ”へ
Ultima IV以降は倫理・徳の導入(アバター思想)や、MMO(Ultima Online)、さらには宇宙飛行など、「ゲーム体験と生き方」 の話へ広がる。
これは 「ゲーム開発レジェンド/哲学的冒険者」 のカテゴリで扱うのが筋だ。
(The New Yorker)

The Computer Game That Led to Enlightenment
Ultima IV was a pioneer in forcing players to grapple with morality.
https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/the-computer-game-that-led-to-enlightenment?utm_source=chatgpt.com参考・出典
- Akalabeth開発・頒布・BASIC実装・ジップロック販売の経緯。(ウィキペディア)
- Akalabeth詳細(Ultima Codexの整理)。(ウルティマコーデックスウィキ)
- Ultima Iの発売、California Pacific。(ウルティマコーデックスウィキ)
- Ultima Iの開発体制(BASIC+アセンブリ/Ken W. Arnold)。(ウィキペディア)
- California Pacific→Sierra移行、倒産と権利の経緯。(ウルティマコーデックスウィキ)
- Ultima IIIとOrigin Systems(自社体制への転換)。(ウィキペディア)
- 倫理RPGへの拡張(Ultima IVの意義)。(The New Yorker)
💬 コメント