![[Programmer Legends #06] Larry Wall ― Perlの創造者と三大美徳](https://humanxai.info/images/uploads/programmer-legends-06-larry-wall.webp)
はじめに
1987年、awk や sed、C では満たせない現場のニーズに応えるため、ひとりのプログラマが新しい言語を生み出した。
それが Perl、そしてその作者こそ Larry Wall(ラリー・ウォール) である。
Wall は単なる言語設計者ではない。彼の活動はしばしば「プログラマというより思想家・文化人類学者的存在」と評される。大学で言語学を学び、NASAやJPLで働き、宣教師的な活動経験を持つという異色の経歴が、そのまま Perl の「人間くささ」や「言語の多様性」へと投影された。
UNIX 系 OS に Perl が標準搭載され、ネット黎明期の CGI スクリプトやログ処理、テキスト変換を支えたことは周知の事実だが、同時に Larry Wall 自身も「パッチの作者」「メーリングリストでの思想的発言者」として、ソフトウェア文化に独自の足跡を残した。
補足:パッチ作者としての顔
Larry Wall は Perl 以前から、patch(1) コマンドの作者として有名です。
-
patch は diff で作られた差分ファイルを既存ソースコードに適用するツールで、オープンソース開発の根幹に欠かせない存在。
-
今でも UNIX/Linux 系統では標準ユーティリティとして生き続けており、Perlと並んで Larry Wall の「もうひとつの代表作」といえる。

ラリー・ウォール - Wikipedia
ラリー・ウォール(Larry Wall, 1954年9月27日 - )は、プログラマ、言語学者、文筆家であり、1987年にプログラミング言語Perlを開発したことによって知られている。また、プログラマの三大美徳を唱え始めたのもラリー・ウォールである。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB
Perl - Wikipedia
Perl(パール)とは、ラリー・ウォールによって開発されたプログラミング言語である。実用性と多様性を重視しており、C言語やsed、AWK、UNIXのシェルスクリプトなど他のプログラミング言語の優れた機能を取り入れている。ウェブ・アプリケーション、システム管理、テキスト処理など、さまざまなプログラムの開発に広く利用されている。
https://w.wiki/6nzf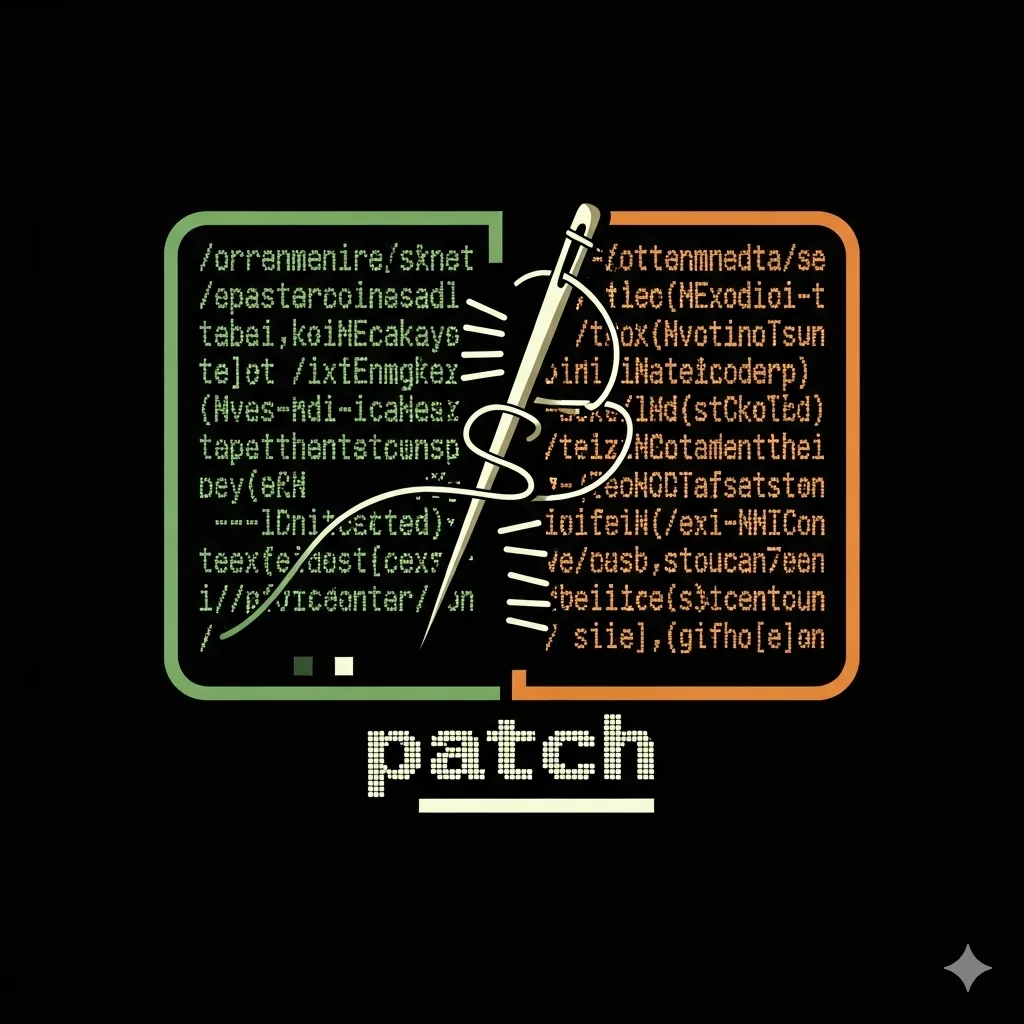
patch - Wikipedia
patch(パッチ)は、テキストファイルにパッチ処理を行うUNIX上のプログラム。「パッチファイル」と呼ばれるファイルに格納された命令群に従ってテキストファイルを更新する。パッチファイル(単にパッチとも呼ばれる)自体もテキストファイルであり、diff を使って元のファイルと更新後のファイルの差分をとることで作成される。パッチによるファイルの更新を「パッチを当てる」などという。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Patch
プログラマーの三大美徳である「短気」が分かりづらいから調べてみた|ホヴィンチ
みなさま、こんにちは。突然ですが、「プログラマーの三大美徳」というものをご存じでしょうか。Perlというプログラミング言語の作者であるラリー・ウォール氏が提唱したものです。内容は以下の三つ。・怠慢 - Laziness ・短気 - Impatience・傲慢 - Hubrisタイトル未設定wiki.c2.comしかし、このなかで「短気」がほかの二つとの違いが分かりづらかったので、この記事でまとめてみます。「怠慢」と「傲慢」そもそもこれらの三大美徳は、一見するとどれも悪徳のよう。しかし、プログラマーにとっては違います。
https://note.com/hovinci/n/n090f6b36a4ef1. 生い立ちとキャリア
Larry Arnold Wall(1954–) はロサンゼルス生まれ、ワシントン州ブレマートン育ちのプログラマ/言語学徒。
1987年の Perl と 1985年の patch(1) の作者として知られ、のちに Free Software Foundation の第1回“自由ソフトウェア発展賞(1998)” も受賞している。(ウィキペディア)
学問的バックグラウンド(言語学 × 自然言語の視点)
-
Seattle Pacific University(SPU) で化学・音楽・プレメディカルを経て、在学中に計算機センターで働きつつ進路を転じ、“Natural and Artificial Languages(自然言語と人工言語)”の学士号を取得。“言語をつくる/扱う”という関心が初期から強かった。 (ウィキペディア)
-
大学院では UC Berkeley(のち UCLA も関与)で言語学を学ぶ。妻のグロリアとともに未記述言語に文字体系を与え、聖書を含むテキストを翻訳するという、言語学と宣教を横断する計画を立てていた(のちに体調などの理由で断念)。(ウィキペディア)
Wall は著述や講演で、プログラミング言語を“自然言語に近いもの”として捉える姿勢を繰り返し語っている。Perl の設計判断にも言語学的比喩(名詞・動詞・トピカライザ等)を用いるのが彼の流儀だ。(ウィキペディア)
宣教師的活動との接点(宗教と言語)
-
SPU 卒業後、夫妻で Wycliffe Bible Translators(シル/SIL International 系) の訓練を受け、“言語を通じて文化へ橋を架ける” ことを志向。宗教と言語/コードの横断という Larry Wall の世界観は、この文脈に強く根ざす。(spu.edu)
-
本人はキリスト教的信仰とプログラミングを対立させず、「科学的視点と信仰の両立」 を語る発言を複数のインタビューで残している。(interviews.slashdot.org)
初期キャリア:NASA/JPL と「実用主義」の源泉
-
大学院後は NASA の JPL(Jet Propulsion Laboratory) に参加。その後 System Development Corporation(SDC → Burroughs → Unisys) へ移り、現場の“報告書処理・ログ加工・運用自動化”という泥臭いニーズに応える形で Perl(1987) を設計する。(ウィキペディア)
-
Perl 以前にも、ニュースリーダ
rn、そして 1985年に差分適用ツールpatchを公開(mod.sourcesに初投稿)。OSS の開発様式=パッチ送受の基盤を整えた功績は、Perlと並ぶもう一つの代表作だ。(ウィキペディア)
「awk/sed/C では足りない現場の穴を埋める」——この発想こそが Perl の出発点。Wall の言語学的な“人間言語”視点と、**運用現場の“実用主義”**が一人の中で合流して生まれたのが Perl だった。(linuxjournal.com)
文化的影響:三大美徳と TMTOWTDI
- Wall は “プログラマの三大美徳”(Laziness / Impatience / Hubris)を掲げ、「怠惰ゆえの自動化・せっかちゆえの性能追求・自負ゆえの品質確保」 という逆説的倫理を提示した。また TMTOWTDI(There’s more than one way to do it) は Perl 文化の合言葉となり、“唯一解よりも表現の自由” を是とする設計哲学を育んだ。(Big Think)
このパートは「思想(言語学/信仰)→実務(JPL/SDC)→道具(patch/Perl)」の順で流し、“技術と言葉/宗教とコード”を結びつける視点を自然に立ち上げています。
次は 「2. Perl 誕生:Why Perl、そして TMTOWTDI」 に進めます。
2. Perl誕生(1987年)
awk/sed/C では届かなかった現場ニーズ
1980年代半ば、Larry Wall は System Development Corporation(SDC → 後のUnisys) のエンジニアとして、UNIX環境でのレポート生成やログ処理、システム管理スクリプトに追われていた。 既存のツールセットは強力だったが、それぞれに制約があった:
- awk:テキスト処理は得意だが、制御構造や外部処理の柔軟さに欠ける。
- sed:ストリーム編集は可能だが、大規模な処理やロジックの表現は困難。
- C言語:柔軟で高速だが、ちょっとしたログ変換やワンショットのレポート生成には「重すぎる」。
この「awk では小さすぎ、C では大きすぎる」という“間の隙間”を埋める道具として、Practical Extraction and Report Language = Perl が設計された。
Wall 自身が後年語ったように、「Perl は科学的に設計されたのではなく、そのとき必要だったから作られた」。まさに現場主義の産物だった。

AWK - Wikipedia
説明なし
https://ja.wikipedia.org/wiki/AWK
sed (コンピュータ) - Wikipedia
sed(セド)は、入力ストリーム(ファイルまたはパイプラインからの入力)に対してテキスト変換などのデータ処理をおこなうために使用されるプログラムである。名称「sed」は「ストリームエディタ」を意味する英語「stream editor」に由来する
https://ja.wikipedia.org/wiki/Sed_(%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF)TMTOWTDI ― 表現の自由を是とする哲学
1987年12月18日、Perl 1.0 が comp.sources.misc に初公開された。
Perl は単なる「便利ツール」以上の文化を持ち込み、すぐに世界中のUNIX管理者・開発者に広まった。
その背景には、Larry Wall が掲げた象徴的なスローガンがある。
「There’s more than one way to do it(TMTOWTDI)」 =「やり方は一つじゃない」。
これは、CやPascalのような**「最適解・唯一解」を求める設計哲学とは真逆**であり、
- “可読性”よりも“書き手の自由”
- “一貫性”よりも“多様性” を尊重する姿勢だった。
この価値観は Perl コミュニティの根幹に刻まれ、CPAN モジュール群やハッカー文化の広がりにも大きな影響を与えた。
![[wiki.c2.com] There Is More Than One Way To Do It](https://c2.com/sig/wiki.gif)
[wiki.c2.com] There Is More Than One Way To Do It
There is more than one way to do it. This phrase is often associated with the PerlLanguage. Unlike other languages (notably Scheme), Perl intentionally contains many simple expressions that are equivalent in result. Its inventor, LarryWall, is trained as a linguist. He has this crazy notion that sometimes phrasing a sentence differently might make its meaning clearer...
https://wiki.c2.com/?ThereIsMoreThanOneWayToDoItネット黎明期とPerlの爆発的普及
1990年代前半、インターネットとWebの急成長が訪れると、Perl は “ウェブのダクトテープ” と呼ばれるほど重要な役割を担った。
- システム管理/ネットワーク運用:
メール配送(sendmail連携)、ログ解析、ユーザ管理スクリプトに広く利用。 - CGIスクリプト:
NCSA HTTPd(後のApache)が CGI を実装すると、Webフォームや掲示板、カウンタなどの動的Webのほぼすべてが Perl で動く時代が到来。 - CPAN(Comprehensive Perl Archive Network, 1995年設立):
世界中のハッカーがライブラリを共有し合う場として、Perl の進化を爆発的に加速。
この頃の Perl は、「UNIXの裏方」から「インターネットの表舞台」へ躍り出た言語だった。
実際、1990年代後半の Web は Perl CGI で彩られ、「.pl」拡張子のスクリプトが至る所に存在していた。
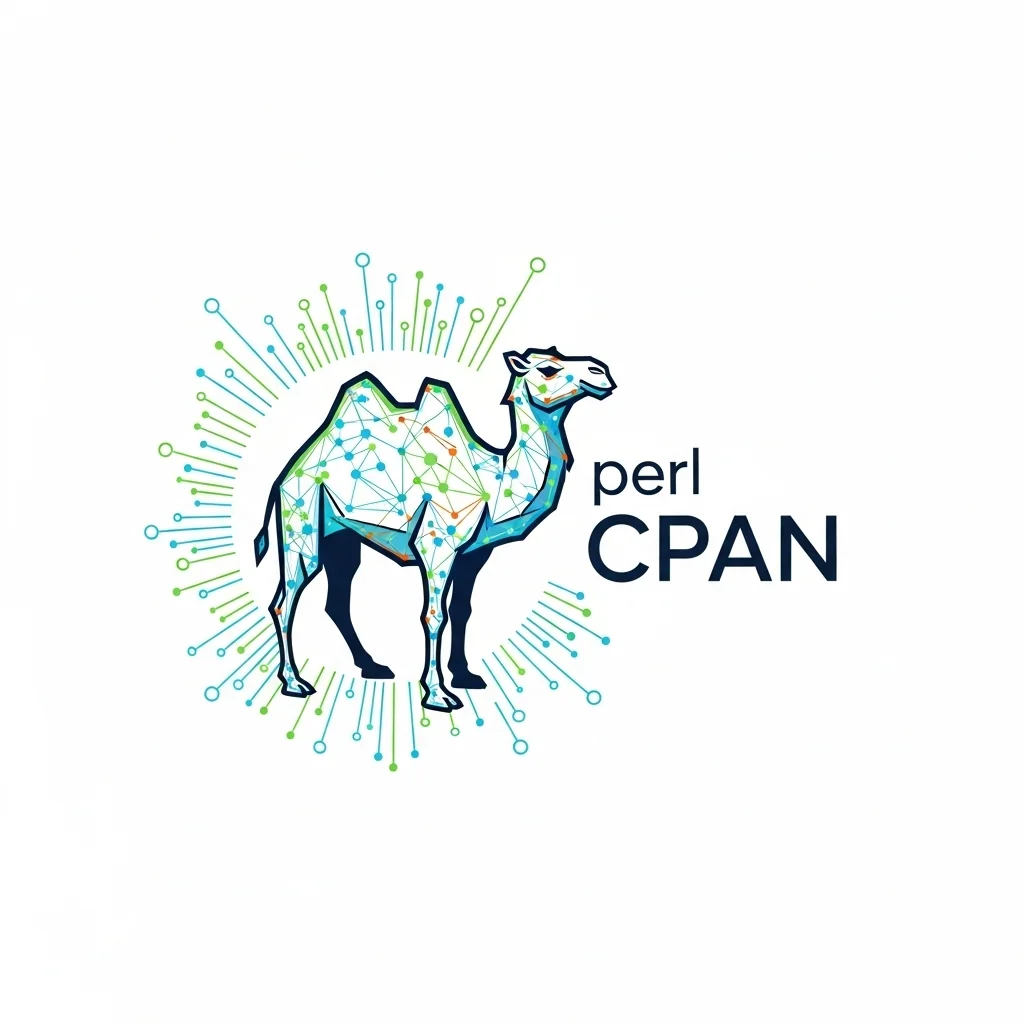
CPAN
CPAN(シーパン、Comprehensive Perl Archive Network)とは、Perlのライブラリ・モジュールやその他のPerlで書かれたソフトウェアを集めた巨大なアーカイブで、世界中のサーバにその内容がミラーリングされている。再利用性・汎用性の高いモジュールが登録されており、Perlプログラマができるだけ車輪の再発明をせずに済むための支援環境となっている。登録モジュールの検索システムも提供されているため、Perlプログラマは望む機能を持ったモジュールを容易に入手することができる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/CPAN
Common Gateway Interface - Wikipedia
Common Gateway Interface(コモン・ゲートウェイ・インタフェース、CGI)は、ウェブサーバ上でユーザプログラムを動作させるための仕組み。現存する多くのウェブサーバプログラムはCGIの機能を利用することができる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface3. 文化と哲学
三大美徳:Laziness / Impatience / Hubris
Larry Wall は『Programming Perl』の文脈で、プログラマの三大美徳をこう位置づけた。
- Laziness(怠惰):
総労力を減らすために先回りして自動化する美徳(結果として他人にも役立つツールとドキュメントが生まれる)。 - Impatience(せっかち):
待たされることを嫌い、レスポンスとUXにこだわる気質。 - Hubris(自負):
恥ずかしくないコードを書くために品質や保守性に責任を持つ姿勢。
これらは“徳目のパロディ”ではなく、現場を前に進めるための動機づけとして定義された(Wall は後年、対になる「勤勉・忍耐・謙虚」も語って対話的に位置づけている)。 (C2.com)
「言語は文化の延長」— Perl Culture の自己認識
1997年のキーノート “The Culture of Perl” で、Wall はPerl文化を「制御と混沌のバランス」で説明した。
- 文化を伝えるのはミームとメタファーであり、Perl文化を理解するにはまず“Larry Wallという発生源のメタファー”を理解せよ、と。
- 「言語は芸術の媒体」 であり、“生きた言語”は共同作業(cooperative effort) として育つべきだ、と述べる。
- その帰結として掲げられるのが TMTOWTDI(There’s more than one way to do it)。唯一解ではなく、多様性を許容する設計と運用 が、環境変化(UNIX→Windows 等)でも生態系を生き延びさせる、と説く。 (Perl.com)
Languages are an artistic medium … I want Perl to be a living language.(要旨)— 1997年キーノートより。 (Perl.com)
Perl Mongers という「場」の発明
Perl の文化は道具(言語) だけでなく、場(コミュニティ) で加速した。
-
Perl Mongers は 1998年に brian d foy らが立ち上げた国際ユーザー会連合。最初のグループ NY.pm は**第1回 O’Reilly Perl Conference(1997年8月)**の流れから誕生し、その後 2000年に The Perl Foundation の一部となる。 (ウィキペディア)
-
公式サイトの説明どおり、各地のPMは**定期的に集まり、技術&ソーシャルを混ぜる“緩い連合”**として動いてきた。実務のTips共有から勉強会運営まで、草の根の運営力が文化を下支えした。 (pm.org)
-
YAPC(Yet Another Perl Conference) はその延長線上にある草の根シンポジウムで、財団が後援しつつ世界各地で開催され、PMと相互作用しながら人と知識の流通を作った。 (yapc.org)
-
財団の回顧でも、NY.pm 結成(1997)→ Perl Mongers 法人化(1998)→ 急速な国際展開という立ち上がりが記録されている。コミュニティという“場”の整備が、Perlの“多様性を受け止める文化”を具体物にした。 (news.perlfoundation.org)
4. その後の活動
Perl 6 構想(2000年)
1990年代後半、Perl は「ウェブのダクトテープ」として圧倒的な地位を築いたが、同時にコード規模の拡大・可読性の問題・モジュール設計の限界などが課題化していた。
2000年7月、Larry Wall は Perl 6 計画を発表。“rewrite of Perl, not just upgrade” を掲げ、次世代言語としてゼロから再設計を試みた。
- 目的:Perl 5 の「継ぎ足し文化」から抜け出し、より一貫性と表現力を持つ言語へ。
- 設計思想:「Perl 5 は良いシステム言語だが、Perl 6 はより人間中心の言語を目指す」。
- 結果:仕様議論が膨大になり、開発は数十年規模の長期化 。多くの試行錯誤の果てに 2019年、言語名を “Raku” と改名 し独立することが正式決定された。
物議と“Perl 5 vs Perl 6” 問題
Perl 6 の長期化と複雑化は、逆にコミュニティ内に分裂や混乱 を生んだ。
- Perl 5 の改良継続 vs Perl 6 への移行 という二重構造が長年続き、外部からは「Perlは停滞した」と見られる要因になった。
- Wall 自身は「Perl 5 は成熟した大人、Perl 6 は実験的な若者」と説明したが、商用開発現場では Perl 5 継続採用が主流となり、Perl 6 の普及は限定的に留まった。
Larry Wall の立ち位置の変化
Perl 6 構想以降、Larry Wall は 「言語設計の実務者」から「文化的・思想的アイコン」 へと比重を移していった。
- 言語仕様やリリースマネジメントはコア開発チームや財団が担い、Wall 自身は方向性や哲学を語る“スポークスマン” の役割に専念。
- 2000年代後半以降、彼は頻繁にキーノートやインタビューで「Perl文化とOSSの未来 」「宗教と技術の対話 」といったテーマを話すようになる。
- 2019年の Raku 改名の際も、Wall は「Perlという名前に縛られず、それぞれの文化が共生する方が健全」として容認の立場を示した。
思想的な影響の持続
たとえ Perl 6 が主流にならなくとも、Larry Wall の言語観は他言語・開発文化に残り続けた。
- Ruby の Matz(まつもとゆきひろ)は「Perl文化に大きな影響を受けた」と公言している。TMTOWTDI への共感が Ruby 設計に反映された。
- OSS文化全般に広がった「草の根ユーザー会」「多様性容認」「逆説的美徳」の思想も、Perl Mongers からの波及。
- 現在でも “Perl の功績” はコードそのものだけでなく、「OSSコミュニティを文化として設計する 」試みの先駆けとして語られている。
5. レガシーと現在
Perl という遺産
今日の Perl は、かつての「Web のダクトテープ」から後退したとはいえ、堅牢なテキスト処理エンジン として生き残っている。
- Perl 5 系列は継続開発中 で、2024年に v5.40、2025年には v5.42 がリリースされた。try/catch 構文、class / role の実験、Unicode 16 サポートなど、現代的な改善が続いている。
- CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) は 1995年以来の膨大なモジュール群を保持し続け、毎日更新が続く。これは OSS 史上もっとも長命かつ持続的な「共有ライブラリ文化」の一つ。
- 運用・科学計算・移行ツール など、いまも「Perl だから強い」分野は残っている(正規表現、バイオインフォマティクス、テキスト変換系のスクリプトなど)。
Larry Wall の存在感
一方、Larry Wall 自身は “現場のリーダー”から“象徴的人物” へと変化した。
- Perl 6/Raku の物議を経て、彼は積極的にコードをリードするよりも、「哲学や文化を語る人」 として位置づけられるようになった。
- カンファレンスやインタビューでは、プログラミング言語を「人間文化の延長 」として語り、宗教と言語学とコード を交差させる比喩を投げ続けている。
- 彼の「三大美徳」や TMTOWTDI は、いまもコミュニティの合言葉であり続け、Perl を超えて Ruby、Python、OSS 文化全般 に影響を与えた。
OSS 文化に残した痕跡
Wall の功績は Perl というツールだけでなく、OSS コミュニティのデザイン にあった。
- patch(1) によって「パッチを送り合う文化」が加速。
- Perl Mongers / YAPC によって「ユーザー会と草の根カンファレンス」のスタイルが普及。
- 逆説的美徳(Laziness, Impatience, Hubris) は、ハッカー文化に「ユーモアと哲学のある自己規律」を与えた。
総括
Perl は 2025年の TIOBE Index で突如「10位」に浮上したように、表面的な人気の浮き沈みを繰り返してきた。
だが Larry Wall の仕事の本質は、ランキングや採用率の外側にある。
「Perlは“帰ってきた”のではなく、最初からそこにあり続けた」。
そして Larry Wall の思想は、言語の枠を超えて「プログラマという生き方」を形づくる文化遺産となった。
まとめ
Larry Wall は単に Perl の生みの親という枠に収まらない。
彼のキャリアは、言語学・文化人類学・信仰・実用主義が交差した異色のものだった。
その結果として生まれた Perl は、1987年から今日に至るまで **「テキスト処理と実用の現場力」**を提供し続けている。
Wall が提示した TMTOWTDI(やり方は一つじゃない)、そして プログラマの三大美徳(Laziness, Impatience, Hubris)は、 Perl の内外に広がり、Ruby や Python、OSS コミュニティ文化全般へ波及した。
2000年代以降、Perl 6(Raku)構想の長期化や人気低迷があっても、
- patch コマンドによる開発様式の基盤
- CPANによるモジュール共有文化
- Perl Mongers / YAPCによる草の根コミュニティ運営
これらは今も OSS 世界の標準となっている。
Larry Wall は「プログラマ」以上に「文化を設計した人」だった。
Perl の歴史は、その思想が形をとった実例であり、Wall の哲学は今も生きている。
だからこそ 2025年の今、Perl がランキングに姿を現そうが消えようが重要ではない。
Wall の残したものは コードの行数ではなく、プログラマの生き方を豊かにする文化的遺産なのだ。
引用で締める
“The three chief virtues of a programmer are: Laziness, Impatience, and Hubris.”
— Larry Wall, Programming Perl
“Languages are an artistic medium … I want Perl to be a living language.”
— Larry Wall, The Culture of Perl (1997 Keynote)
参考リンク
-
Larry Wall – Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall (経歴、生い立ち、Perl・patch の作者としての紹介)
-
Perl – Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Perl (言語の歴史、リリース年表、主要バージョンの解説)
-
Perl 5 Version History – Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Perl_5_version_history (5.x 系のリリースと機能差分、2025年現在までの詳細)
-
The Perl Foundation https://www.perlfoundation.org/ (コミュニティ活動、グラント、Perl Mongers や YAPC の母体)
-
Perldoc – perldelta https://perldoc.perl.org/perldelta (最新リリースで追加された機能の公式ドキュメント)
-
MetaCPAN – Recent Uploads https://metacpan.org/recent (日々更新される CPAN モジュールの一覧)
-
The Culture of Perl (1997 Keynote, Larry Wall) 要旨・資料アーカイブ (「言語は文化の延長」と語った有名な基調講演)
-
Wikiquote: Larry Wall https://en.wikiquote.org/wiki/Larry_Wall (三大美徳や Perl 哲学に関する名言集)
-
C2 Wiki – Laziness, Impatience, Hubris https://c2.com/cgi/wiki?LazinessImpatienceHubris (プログラマの三大美徳の解説ページ)
💬 コメント