![[Culture] AIと自分図書館論 ― 立花隆の猫ビルから個人知の変容へ](https://humanxai.info/images/uploads/culture-ai-private-library.webp)
猫ビルという象徴
立花隆は生涯にわたり膨大な書籍や資料を収集し、それを「猫ビル」と呼ばれる自宅兼図書館に蓄積した。 そこから記事や書籍が生み出される「巨大アーカイブ型ジャーナリズム」は、日本の知的生産の象徴となった。
猫ビルとは、言い換えれば「個人が公共図書館を丸ごと背負う試み」だった。

立花隆 - Wikipedia
立花 隆(たちばな たかし、本名:橘 隆志 1940年〈昭和15年〉5月28日 - 2021年〈令和3年〉4月30日)は、日本のジャーナリスト、ノンフィクション作家、評論家。執筆テーマは、生物学、環境問題、医療、宇宙、政治、経済、生命、哲学、臨死体験など多岐にわたり、「臨死体験」・「日本共産党の研究」など、詳しくは下に書いてあるが、多くの著書がベストセラーとなっている[3]。その類なき知的欲求を幅広い分野に及ばせているところから「知の巨人」のニックネームを持つ[4]。
https://w.wiki/3XYC
事務所「猫ビル」と蔵書
「立花隆」の記事における「事務所「猫ビル」と蔵書」の解説
https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%80%8C%E7%8C%AB%E3%83%93%E3%83%AB%E3%80%8D%E3%81%A8%E8%94%B5%E6%9B%B8猫ビル ≒ AI
しかしAI時代、膨大な文献を自分で集める必要はなくなった。
AIが検索し、要約し、構造化して提示してくれる。
つまり「猫ビル」そのものがAIへと変換されつつある。
膨大な物理的書庫を必要とせず、知識への入口は手元に常に存在する。
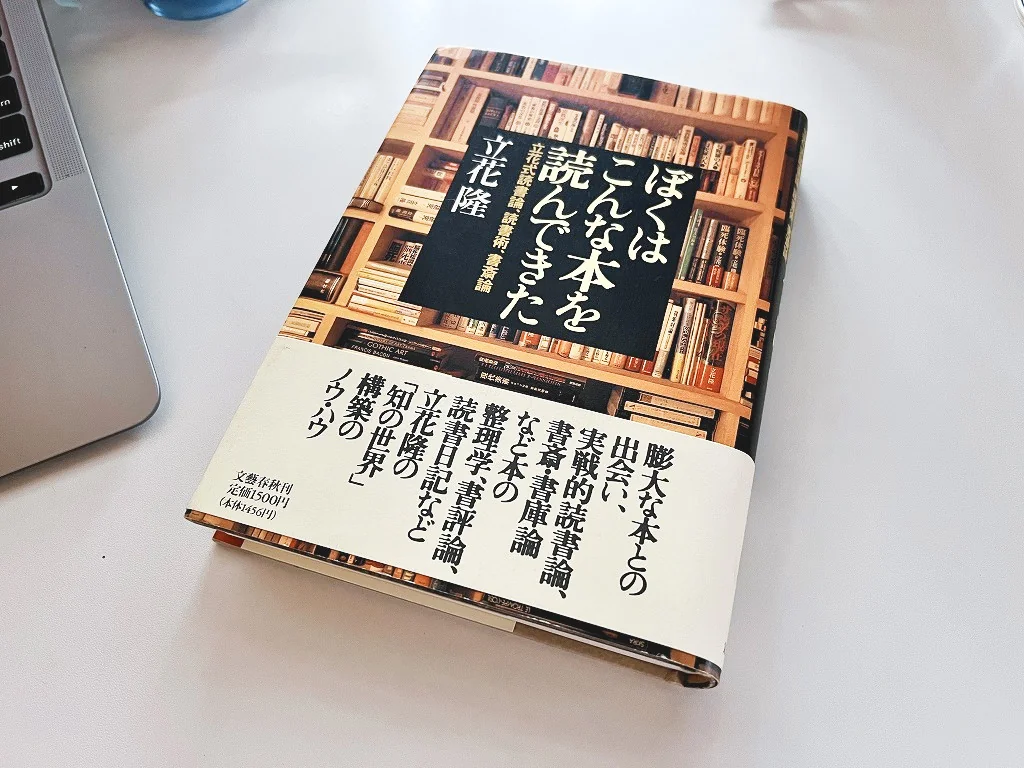
自分図書館という変貌
AIを介して記事を書き、読み返し、修正し、積み重ねることで、ブログ自体が「自分専用の図書館」へと変貌していく。
- AIが文献検索を肩代わり → 思考に集中できる
- 記事が外部メモリとなり、繰り返し読むことで思考が循環する
- 記事が記事を呼び、アーカイブが自己増殖する
このプロセスは「猫ビルを背負う」代わりに「AIを背負う」ことで実現している。
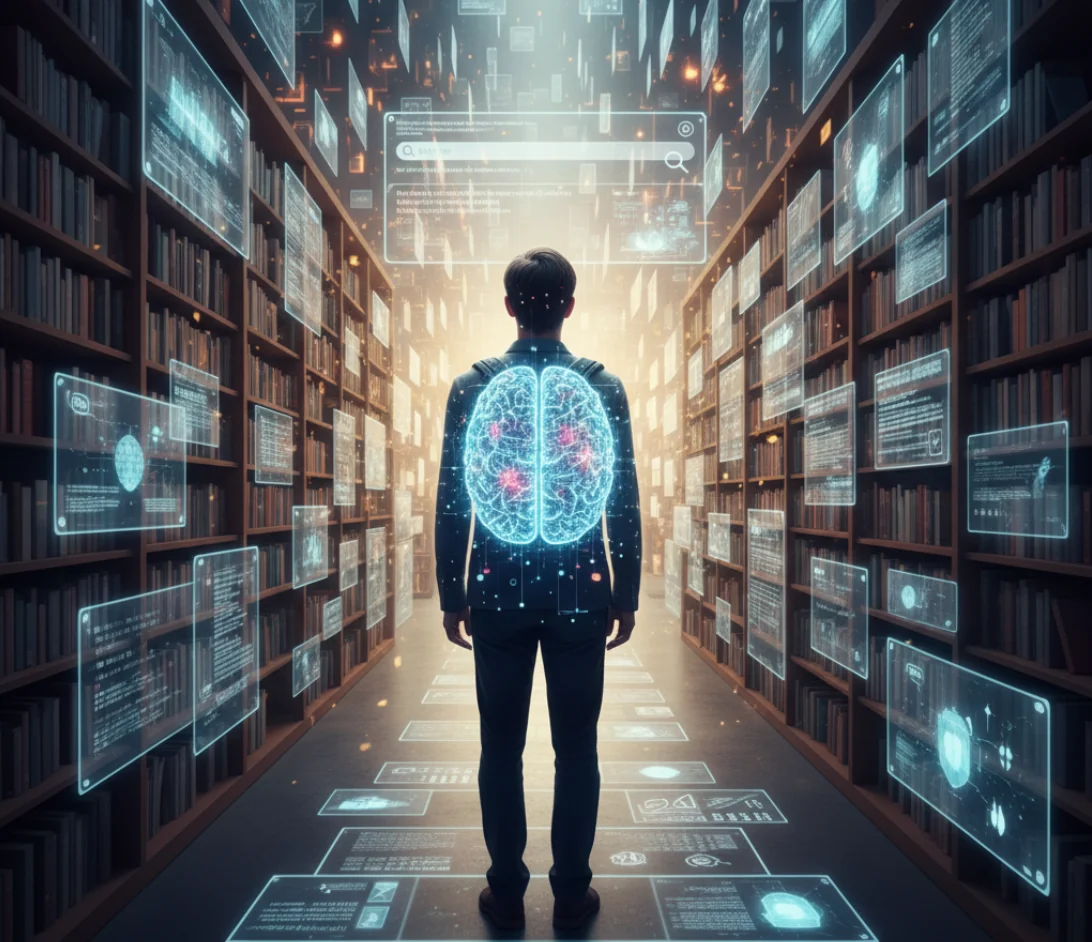
メリットとデメリット
-
メリット
- 調査や引用の労力が大幅に減る
- 個人の思考に最適化されたアーカイブができる
- 思考の深化と再帰的循環が自然に起こる
-
デメリット
- 他人にとっては「自分図書館」にすぎず、公共性が薄い
- 読者目線では、散文的で雑多に見えることもある
孤独から文化へ
それでも「孤独な自給自足の記録」が積み重なったとき、それは一人のための図書館であると同時に、文化の証明にもなる。 立花隆の猫ビルがそうだったように、AI時代の「自分図書館」もまた、個人の営みを超えて残り続ける可能性を持っている。
立花隆の猫ビルから個人知の変容へ
自分の興味のあるテーマをAIと雑談を交えつつ掘り下げて、記事を書くことが増えましたが、その結果、最近書いた記事はどれも面白く何度も読み返しています。
そこでふと
「この現象は一体なんだろう?」
と・・。
2000年前、ネット黎明期の頃 ―
今と同じようにWEBを作り、Perl、PHP、Java、Visual C++などの書籍を読み、情報をアウトプットしていました。
現在のような静的ジェネレーター『Hugo』、『CMS』、『ブログサービス』など便利な物はなく、テキストエディタでHTMLを手書きしWEBを作るのが当たり前。
git もなく、あるのはFTPだけ。
知ってる事・学んだ事をアウトプットし、アウトプットした情報を読み返しても、面白いとは感じなかった気がします。
しかし、今はAIが分からない事を教えてくれ、対話内容に付随する情報を短時間でかき集め、私用にカスタムした情報をまとめてくれます。
その結果、興味のある記事が量産され、繰り返し読むのに耐えられる記事が増加。
アイキャッチ画像が、「書籍の背表紙」で、本棚を眺めるのと同じ効果を生み、 クリックで開けば、本文、目次、見出し、画像、引用、リンクがある。
書籍と違い、余分な情報を削ぎ落す為、短く纏まっていて、長文を読むのも楽な上に面白い。
リアルの書籍は、最低でも200ページぐらい程の情報が必要なのに対し、AIの書いた記事にはそれがない。
尚且つ、AIのやる作業を、人力で完結させようと思うと大量の文献ー
立花隆氏のような「猫ビル」が必要。
しかし、現在は、
『 猫ビル≒AI 』
になっており、猫ビル自体がAI化して相談者に合わせて本を執筆する。
その結果、ブログが自分に合わせた図書館に変貌していく。
今ま何となくディープリサーチでAIに情報をまとめてもらい、記事を書き、それを読んで学習を重ねてきましたが、その結果、こんな現象が起こるとは思っていなかったので、冷静に振り返って驚きました。
ただ、これにはデメリットがあり、あくまで ”自分専用の図書館” の為、他人が読んでも面白くない。
以上が、昨晩AIと対話する中で分かった事ですが、メモも含めてこの内容を記事にして残しておきます。
無論、それでも一冊の書籍で体系的に学ぶことの重要性は無くなっていませんし、まだ本を買って読んではいます。
これから先、ブログを作り続けていく事で、また価値観が変貌していくと思うので、あくまで現時点での意見です。
人は変わっていく生き物なので。
💬 コメント